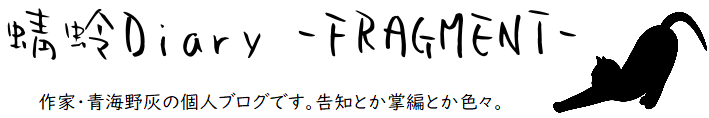お題:私を愛したスパイ
私が辻先輩に声をかけたのは、十名程の部員がざわめく部内でもいつも一人でいる彼が一番話しかけやすそうであり、また、少し親近感を覚えたからだった。
彼はいつも文芸部室の窓際の陽だまりにパイプ椅子を置き、細長い足を組んで難しそうな本を静かに捲っていた。部室に舞う埃が秋の陽光を受けキラキラと光り、そこだけ時間がゆっくりと穏やかに流れているように見えた。
その視線の先の物語に向けられる、薄いフレームの眼鏡の奥にある一見冷たい瞳には、時折温かな優しさが灯る事が分かるくらいには、私は彼を観察していた。
躊躇する足を義務感で動かし、彼の横に立つ。
「何を、読んでるんですか?」
初めてのコンタクトには、緊張で声が上擦った。
彼はゆっくりと私を見上げると、次いで本の背表紙を私に見せ、また読書に戻ってしまった。立ち竦む私は知らないタイトルに次の言葉が浮かばず、スカートを掴んで窓の外に視線を逃がす。そんなやり取りを、恥ずかしさを堪えながら私は、私の好きな本を彼が掲げるまで一週間程続けた。
それが私の文芸部仮入部後の行動で、正直、一冊の本も読んでいない。
何で私が選ばれたんだろうと、泣きたい気持ちだった。
生徒会に所属している私が、会長からの命令で文芸部に潜り込んだのは、二週間程前。
以前から部費の僅かな水増し受給が疑われていたこの部へのスパイに私が指名されたのは、会長曰く「お前、本好きだろ」という理由だけだった。元々文芸部に入るつもりだったのに生徒会に無理矢理引きずり込んでおいてこの仕打ちですか、と密かに視線に込めた不満は、会長のオーラに呆気なく弾かれる。確かに生徒会でも地味な私は、潜入捜査には適任なのかもしれないけれど。
とは言えスパイなんて柄じゃない私は、その心得を探るため、暫くはスパイ小説を読み漁ったりした。
重要なのは、そう、ターゲットと仲良くなる事。
やがて私の地道な活動が実を結び、彼の定位置の隣には、私のパイプ椅子が並べられるようになった。
二人並んで読書する様子を他の部員から「オシドリ夫婦」なんて揶揄される事もあり、その度に胸が爆発するような恥ずかしさを感じて、私は聞こえなかったフリで手元の本に視線を落とすしかなかった。辻先輩が相変わらずの静けさでヤジを否定しない事を、なんだか嬉しく思いながら。
☆
秋も更け、仮入部から二カ月が過ぎようとしていた頃。ふと耳に入った図書購入の話題に、私は忘れかけていた使命を電撃の様に思い出した。
いけない、文芸部生活をすっかり満喫してしまっていた。
私は本を閉じ、右隣に座る先輩を見上げる。
「あ、あの、文芸部の部費の申請って、誰がしてるんですか?」
さりげなくそんな質問が出来るくらいには、彼とは会話をしてきたつもりだった。彼はいつもの冷たい瞳で私を見下ろし…
「綾」
唐突に下の名前で呼ばれた私は椅子から落ちそうになるほど驚いた。
「ひゃ、名前!?」
「あれ……ダメかな。夫婦なら名前で呼ぶものかと思ったけど」
突然何を言うんだこの人は。その言葉と、いつも物語に向けられる優しい瞳が私に向いている事に、歓喜と混乱が脳内で渦巻く。
「だ、だめ、では、ないですけど」
「よかった。ところで綾、君は生徒会だろう?」
恥ずかしさに下ろしかけた視線は、驚きと共に再び彼の目を見上げた。
「この高校は部活のかけもちは禁止してないが…君がここに来た目的は、その部費に関する調査だ」
「なんで……それを」
気付くと部室は、私達二人だけになっていた。皆本の追加購入に外出したようだ。
自分の鼓動が聞こえそうなくらい静かな部屋で、辻先輩の右手が私に近付く。彼は人差し指を立て、それを私の唇に押し当てた。
「僕はこれからも、君の隣で心地良く本を読んでいたい。いつか本当に夫婦になれればいいとも思っている」
湯気でも出てるのではと思う程私の体は熱く、心臓は限界のスピードで脈打っていた。
「……はい」
「だから、僕が数字に細工をしているという事は、二人の秘密にして欲しいんだ」
彼はそう言い、眼鏡を外して前髪を掻き上げた。そこにいたのは、生徒会役員会計担当の、石田先輩だった。
「ええっ!?」
「石田は僕の双子の弟の名字だよ。家庭の事情ってやつでね。髪型と視力以外は瓜二つだから、たまに入れ替わらせてもらってる」
彼は眼鏡をかけ直し、
「要するに、僕も文芸部から生徒会に潜り込んでるスパイだったって事さ。読みたい本は高いものが多くてね」
と悪戯っぽく微笑んだ。
「騙して悪いと思ってるけど、さっき君に言った気持ちは、本当だよ」
スパイが籠絡される。それはよくある話。でも私の心は決まった。
☆
後日生徒会室で、私は胸を張って会長に報告する。
「文芸部はシロでした!」
眼鏡を外した辻先輩が、私に向けて微笑む。
楽しい日々が始まる予感で、世界が少し、輝いた。