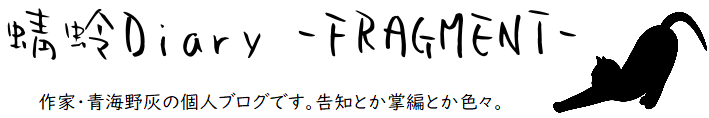お題:手紙
春の爽やかな朝日の差し込む明るい喫茶店には、似つかわしくない悲しげなジャズピアノが、誰からも忘れ去られたように流れていた。
結婚してからもう数年が経つが、こうして朝食を外でとるというのは、意外にも初めてのことで、二人で微かに驚いて笑ったりもしていた。
カウンター席から眺める外の風景は、慌ただしくもありふれた日常を映し出していて、僕の精神を激しく揺り動かし続けた音のないやりとりも、今朝僕の心に深く入ったヒビも、そんなものはただの長い夢だったんじゃないかという幻想にふと囚われる。
それでもそっと目を閉じて、胸ポケットから皮膚に伝わる感触に心を向けると、それは確かにそこにあって、ほっとしたような、やり切れないような、悲しい諦めにまたゆっくりとまぶたを開ける。これは疑いようもない、現実だ。
いつものように右隣に座る君が、今朝見たという夢の話を楽しそうに喋っている。
君を悲しませてはいけない。一つの傷も付けはしない。だから僕は、日常を装う。
君の口が放つ音の抑揚だけを聞いて相槌を打ち、楽しげな雰囲気だけを感じて笑う。
言葉の意味まで掬い取れない。心はただ、あなたの残した最後の手紙を、そこに書かれた文章を、想い浮かべては何度も反芻するだけだった。
微かな悲しみと共に、叫びたくなるような寂しさと共に、意味も分からずに微笑んでは、味気ないパンを噛み締める。
やりとりのきっかけは、一通の投函誤りの手紙だった。
珍しく妻より早く起きた僕は、郵便受けにあった手紙の送り主をろくに見もせずに封を切り中を読んで、ようやく僕に宛てられたものではない事に気付いて血の気が引いた。開けてしまったことで返送する事も出来ず、かといってこのまま捨てるには心が痛む程の苦しい想いの言葉が、そこには綴られていた。
暫く悩んだが、僕はペンと便箋を探した。誤配送の報告と、読んでしまった事の深謝と、持てる限りの力を使って慰めの言葉を綴り、心の中で謝りながらポストに入れ、顔も知らないその人の幸福を願った。やがて日常の中で忘れかけた頃、ひらりと舞い込む様に返事が届いた。今度は誤配送ではなく、僕宛の。
そこから、奇妙な手紙のやりとりが始まった。
始めはどこかぎこちなかったけれど、あなたは傷を吐き出し、僕も過去の闇をさらけ出し、微かにすれ違いながらも、恐る恐る寄り添うような、優しさを唄い合うような言葉が、二か月ほど取り交わされた。僕は朝の投函が何よりも楽しみになり、いつも早く起きては、妻に見つからないようにその手紙を読み、返事を書いた。
いつの間にか僕は、あなたの傷と悲しみの深さに掴まれ、あなたの計り知れない優しさに酔いしれ、抜け出せなくなっていた。僕の手で、この腕で、あなたを慰めたいだなんて、思うようにさえなってしまっていた。
それが許されるはずもない事は分かっていながら、あなたを求め、手を伸ばし、許されるはずがない事に気付いて、絶望する。あなたが僕の手を取れば、あなたを傷付け今もあなたの心に居座るその男と同じ存在に、僕は成り下がってしまう。
無音のやりとりは心地いいものではなくなった。あなたの綴る言葉から、あなたの手が僅かに僕に向けられている事に心の底で喜び、軋むように痛みながら、僕はこの穏やかな日常を破壊することも厭わないとさえ思うようになり、あなたに、そう伝えもした。
あなたの最後の手紙は、朝日の差し込む郵便受けの中で、静かに眠っていた。そして今は、僕の胸ポケットに。
さよなら
どうかお幸せに
私はあなたを忘れない
最後の一文は、きっと、嘘だ。あなたは僕を忘れる。そうでなくてはならない。あなたは僕を忘れなくては、ならない。
そしてその甘い囁きのような、呪いのような言葉に、僕は永遠にあなたを忘れられなくなる。
それでも僕は、助けられたのかもしれない。
あなたが、世界のどこかで音もなく守ってくれたこの日常を、僕も命がけで守ろう。
「でさ、その人がまた変なこと言うんだよー」
君の楽しそうな笑顔を視界の右端で確認しながら、僕は決して窓の外の景色から目を離さなかった。まるでそこで揺れる葉桜の新緑を愛しむようにしながら。今の僕は、君の方を向けない。
心の中で激しく渦巻く様々な想いが溢れて、抑え切れなくて、零れ出して、僕は器用にも、左目だけで泣いていた。
君は気付いていないだろうか。いや、鋭い君のことだから、気付いていながら、心に不安を抱えながら、楽しい話を続けているのかもしれない。
そんな君の不安を取り払うため、僕は嵐のように荒れ狂う心を抱えて、日常を演じ続ける。
君の話を聞いて笑いながら、琥珀に揺れる冷めたコーヒーを啜ると、ほろ苦さの中にほんの少しだけ、涙の味がした。