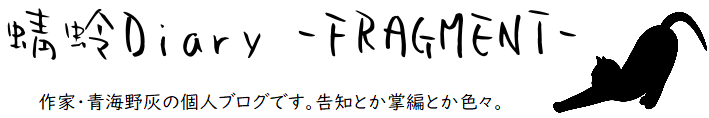お題:猫とアオゾラ
盗んだパンを抱え、汚れた灰色の石の街を裸足で駆け抜けた。身に纏うのは街よりも汚れたボロ一枚。背に浴びる怒号は風よりも早く遠ざかる。私の足は、富と贅肉を持つ大人には決して捕まらない。
暗い路地裏の塵捨て場に身を隠し、乱れた息のままパンを齧る。足の裏に刺さった硝子片を抜き取り、腰袋に入れた。袋の中にかちりと落ちるその音を聴くと、少しだけ心が弾む。
笑みを浮かべ再びパンを齧る私の耳は、背後の微かな足音を捉えた。飛び退り身構えると、そこにいたのは猫。
私に驚いたように真っ白の体を強張らせ、碧の瞳でこちらを見上げていた。戯れにパンを千切って投げると、器用に後ろ脚で立ち、汚れた地面に落ちる前に口で捕らえた。楽しくなった私は、何度もそれを繰り返した。
やがて彼女は、私の無二の親友となった。共に水溜りで喉を潤おし、盗んだパンで空腹を紛らせ、汚れた街を風の様に駆けた。
私はその純白の雌猫を、リリィと呼んだ。それはかつて、朧げな記憶の中私を抱き上げた人間が私を呼んだ名だった。私を捨てた、母と呼ばれる生き物が。
夜は路地裏の袋小路で、拾った麻布に包まった。腰袋に貯めた硝子片を月夜の冷たい明りに翳すとキラキラと輝く。私はそれを眺めるのが好きだった。リリィにも特別に見せてあげた。彼女の碧の瞳が輝きを反射し、星空の様に煌めいた。きっと宝石というものは、こんな風に光るのだろう。
「ねえリリィ、私いつか本当の宝石に囲まれてみたい。お腹が膨れなくても、その輝きはこの胸を満たしてくれる気がするの」
リリィは何も言わずに目を閉じた。見果てぬ憧れと共に彼女を抱いて、私も眠る。
ある日マルシェからいつもの様にパンを掠め取ると、すぐに私の腕が掴まれた。
「漸く捕まえたぞ泥棒猫」
見上げると、いかにもガラの悪い連中が私を囲んでいた。待ち伏せされていたらしい。
「どうせ余って捨てる物をもらって何が悪いのよ」
「なら俺達のやる事にも文句は言えないわけだ」
麻袋を頭に被せられ、男達に手足を掴まれたまま、私はどこかへ連れて行かれた。大声で暴れても、街の誰も助けてはくれなかった。
暗い廃屋で、食事も与えられないまま数日間に渡り男達から幾度もの乱暴を受けた。
余って捨てる物――。木屑と体液と空腹と疲労に塗れながら、私は腐ったパンと同じ、いや、それ以下の存在なのだと思い始めていた。
生きようとする気力は枯れ果て、僅かに残された力で舌を噛み切ろうとした時、近くで酒に酔い潰れていた男が突然の悲鳴を上げた。と同時に、猫の威嚇の声。見れば、碧の瞳の純白の猫が、男の頬から奪った鮮血をその爪に滴らせている。
「リリィ!」
激高した男の蹴りを彼女はひらりと避け、男に向け再度爪を振るが、衣服に阻まれ動きが止まる。その彼女の細いお腹を男は蹴り飛ばした。悲鳴の様な声を上げ床を転がるリリィはそれでも立ち上がり、なお男に向かおうとする。
私は、何をしている。彼女が懸命に戦っている今、何を呑気に寝転んでいる!
軋む体を動かし、床に散ったままの私の服の腰袋に手を入れ、そこにあるものを掴む。雄叫びを上げ走り寄り、振り向いた男の顔に目一杯の硝子片を叩き付けた。顔を押さえて叫ぶ男を横目に、裸のままリリィと共に駆け出す。叫びを聞きつけた別の男達がすぐに別室から出てきた。
「おい、あいつの背中!」
「白百合の烙印?」
「誰も気付かなかったのか!生かして売れば金になる!追え!」
男達の声を背中で聞きながら、連日の地獄が幻の様に足は軽やかに地を蹴った。廃屋を出ると外は驟雨。冷たい雫が全身を叩き、こびり付いた穢れを洗い流していく。
ここはどこだ。そんなのはどうでもいい。ただ走る。何者にも捕まらない程速く。
駆けながら、私の耳は遥か過去の声を聴いていた。母の優しい声を。
――白きユリは純潔の花。どこまでも無垢でありながら、静かなる威厳を湛える――
何故今、こんな言葉を思い出すのか。あなたに捨てられたあの日から、私は無垢では生きられなかった。
侯家の妾子であることを示す背中の烙印が熱く疼く。
――強く生きて、誇りを持って死になさい――
記憶の中、痣だらけの母は泣いていた。私は守るために捨てられた。何故今になって、気付くのか!
息は切れ、足はもつれ、地に膝を付いた。倒れる体は辺り一面に張った水に迎えられる。
雨はいつの間にか止み、凪いだ水鏡は果てしない青空を映す。片頬を水につけたまま目を開けると、空に映る私がいた。
煤と塵が雨で流れた純白の髪、碧の瞳。
首を動かし視線を前方に向けると、数ヤード先に佇むリリィが私を見ていた。
「行って、リリィ。ありがとう」
せめて終わりだけは、無垢のまま、誇りと共に。
天地の蒼穹の中、別れの挨拶の様に一声鳴き、静かに歩き去っていく。
彼女の足元から広がる水の輪は、優しく私を包み、陽光を反射し、碧い宝石の様に煌めいていた。