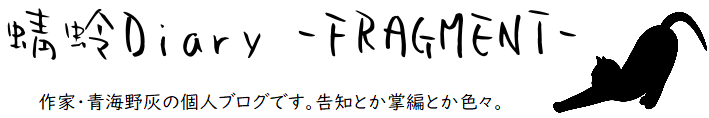お題:無口な人
釣竿とバケツを持って、私は家を出た。
立ち並ぶビルの廃墟は、それを覆う蔦や緑の葉を、今日も風に揺らしている。風に乱され視界を遮る邪魔な髪を耳にかけ、 緑の茂る廃墟の街を歩く。この長い髪が煩わしいと思う事もあるが、これを切る権限を私は持たない。
港に着き、餌を付けた針を海に投げ込み、魚を採る。私の駆動維持に必要な量を確保した後、焚き火でそれを焼き、食べる。
「なーう」
また来た。
声のした方を見ると、いつも私の食事の邪魔をする一匹の黒猫が歩み寄って来る所だった。足元の小石を拾い猫に向けて投げるが、奴は私の脅しを気にもせず側に座り込んだ。仕方なく、食べていた魚の身をちぎり、猫の足元に置く。猫はハクハクと熱そうにそれを食べた。
食事の後、主の墓に向かう。草原の丘の上の、木の枝を組んで作った簡素な十字架がそれだ。隣に立派な石の十字架があり、それを模倣して私が作った。妻の隣に主を埋葬し、そこに毎日訪れるというのが、死に際の主が私に与えた最後の仕事だった。
人類が未知のウィルスにより死滅してから、十ヶ月が経つ。主は何らかの抗体があったのか、その最後の人間だった。私は4年、主の世話をしたが、空気中に蔓延するウィルスの殺意は、やがて主の抗体を上回った。
いつも5分ほど墓を眺めた後、家に戻る。この行為がどのような意味を持つのか、私は理解していない。
家に帰った私は、主が死の直前に出したもう一つの指示の録画映像を視界の端に映しながら、主の部屋の扉を開けた。主が死んでから初めて入る部屋は、埃っぽい匂いがした。
「次のX月X日、僕の机の引き出しを開けてみてくれ」
衰弱した主の疲れた笑顔が、映像の中でそう言っている。今日が、指定されたその日だった。
木製の机の引き出しを開けると、折り畳まれた紙と、小型のディスクが入っていた。紙を広げ、そこに書かれた文字を読む。
*
今日は君を起動して丁度5年になる日だ。
僕は妻を失った絶望を埋める為、孤独の狂気に蝕まれながら妻に似せて君を創った。
だが君に妻を重ねようとする度、それは妻への冒涜のように思え、最後のパーツを君に組み込めなかった。
しかし共に過ごすうち、君の存在は私にとって大切なものとなった。人間の心というのは、難しいものだ。
この最後のパーツが、君へのプレゼントだ。どうか受け取って、再び僕の伴侶として共に生きて欲しい。
誕生日、おめでとう。
*
末尾の日付は、主が死ぬ二ヶ月前だった。この時の主はまだ、自分が死ぬとは思っていなかっただろう事が文面から読み取れる。
私は紙を机に置き、ディスクを取った。服を捲って胸部のハッチを開きディスクを挿入すると、胸元からじわじわと熱のようなものが全身に広がっていった。
「あ、ああ……」
それは彼と共に生きた記憶。出会いと、愛と、そして、別れの記憶。これは主の妻の――いや、私の心と想いを移植した思考ユニットだ。
私は家を飛び出し、彼の墓へ走った。簡素な十字架の前で私は草原に崩れ落ち、叫ぶように泣いた。
あんまりです。酷い仕打ちです。誰もいない、あなたさえいない世界に、私だけを呼び戻すなんて。
泣いても、泣いても、悲しみは薄れなかった。作られたこの体は、泣き疲れるという救いさえ、もたらさなかった。
何時間過ぎたか分からない。ふと私の耳に、猫の鳴き声が聞こえた。顔を上げると朝焼けのオレンジの中、いつもの黒猫が緑の瞳で私を見つめていた。
「……リヒト、あなただったのね」
私の死の数日前に彼が拾ってきた小さな黒猫は、立派な大人になっていた。容姿の印象とは真逆の「光」の名を付けた彼を、笑った事もあった。
リヒトは甘えるような声で鳴きながら、私の腕に体を擦りつけた。
「お腹空いたの?」
何ヶ月もそうしていたように、私は海へ行き釣竿で魚を採り、焚火で焼いてリヒトと分け合った。その美味しさに、涙を流しながら食べた。風が髪を撫で、ビルの緑と海の青を揺らした。それがとても美しくて、私はまた泣いた。
彼は何故、私に思考ユニットを与えたのだろう。心を得た私の嘆きなど容易に想像できただろうに。
せめてあなたが生きている時になら、あの時言えなかったさよならが、伝えられたはずなのに。
◆
今日も私は釣竿を持って海へ向かう。横を歩くリヒトは機嫌が良さそうだ。
彼は私に、私として生きる事を望んだのかもしれない。無慈悲な運命に断たれた命を、やり直して欲しかったのかもしれない。それはとても残酷な、けれど彼の切実な魂の願いなのかもしれない。
それなら私は、彼の望むようにかつての私として、世界と彼を信じて生きよう。
あなたを愛した記憶は、私と共に永遠に、そして今も確かに、私の胸の中に生き続けている。