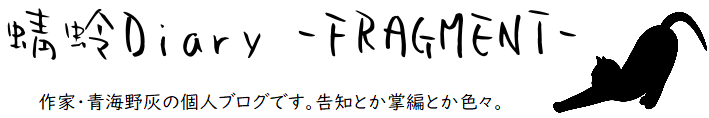ミス・ハダリーは、今日も美しい。
白く、陽の光を透かすような、その繊細な指先で。
――ともすれば世界さえ、滅ぼしてしまいそうなほどに。
.
苔生す石畳。
無数の草花。
古い教会を再利用しただけのオンボロの建物。
何も変わっていない。ここは、空気が緩やかで、優しい。
古びて蔦の絡んだゲートをくぐると、彼女の姿はすぐに視界に入った。
沢山の植物に囲まれたこのヴィクトール孤児院で、彼女はいつも、庭に咲く花を愛おしそうに眺めていた。
僕の来訪に気付いたのか、彼女が顔を上げこちらを見る。さらりと流れるプラチナの髪が五月の太陽の光を照り返し、エメラルドの瞳が、大きく見開かれていく。僕の心臓が、急速に温度を上げながらギシギシと軋むように痛む。
「フランク君? フランク君なのねっ?」
彼女は手にしていた如雨露を傍らに置くと、僕の名を呼びながらこちらに駆け寄って来る。僕は帽子を外すと、精一杯の余裕を演じ、微笑みを浮かべて応じた。
「お久しぶりです、ハダリーさん。僕ももう成人男性ですよ。子供の頃の愛称で呼ばれるのは恥ずかしいです」
「そう? じゃあ、こうしようかしら……。ようこそお出でくださいました、フランシス・エワルド様。本日はどういったご用件で?」
「……フランクで、いいです」
彼女は目を細め、「ふふっ」と悪戯っぽく笑う。気が、狂いそうになる。
「冗談は置いといて、本当に今日はどうしたの? 人づてで考古学者になったと聞いたけど、すごいのねえ」
「いえ、教授のツテに縋っただけで……。今日は、珍しく休暇が取れたので、自分が育ったこの場所を、久しぶりに見に来たんです」
「あら嬉しい。さあ、どうぞ入って、子供たちも喜ぶから」
孤児院の中は、僕がここで過ごしていた十年前から少しも変わっていなかった。レースカーテンから差し込む光や、壁や床のウォルナットの柔らかな木質が、この場所に満ちる優しさを静かに物語っている。
僕は、物珍しげに群がってきた子供たちに、手土産に持参した菓子を振る舞い、暫し遊び相手をさせられた。エネルギーを持て余している子供の相手は本当に疲れるが、ハダリーさんが優しい笑みを向けてくれるので、手を抜く訳にはいかなかった。
やがてはしゃいで疲れ切った子供たちが全員昼寝を始めると、ようやくの静けさが訪れる。僕は疲労感を抱えながら、ハダリーさんが淹れてくれたハーブティを飲み、ようやく一息をついた。
「お疲れ様、フランク君。きみももう、立派なお兄さんになったのねえ」
「『お兄さん』はやめてください。さっきも言いましたが、僕はもう大人ですよ」
彼女が目を細める。無制限に残酷な優しさで。
「わたしにとっては、ここを巣立って行った子たちは、みんな子供みたいなものよ」
「ハダリーさん、」
――僕はもう、あなたを娶る事だって出来ます。
いつまでも子供扱いされる苛立ちに背中を叩かれ吐き出すように言った僕の言葉に、彼女は寂しげに微笑んで、目を伏せた。
「……わたしを、好きになっちゃいけないよ。それはきみがいくつになっても変わらない」
「どうしてですか」
困ったように眉を寄せる彼女の表情に、僕は泣きそうになる。
違う、僕は、あなたを困らせたいんじゃないんだ。
でも口をついて言葉は出る。
「あなたの容姿が、十年前から微塵も変わっていない事と、関係があるんですね?」
触れてはいけないと思っていた。
傷付けてしまうかと思っていた。
でもこの壁を越えていかなければ、僕は彼女の心に歩み寄る事さえ、できない。
「……やっぱり、おかしいよね」
「おかしくなんてないです」
彼女は静かに首を振り、僕の否定を否定した。
「ううん。おかしいんだよ。それは何よりわたしが解ってる」
ベッドですやすやと眠る子供たちを愛しげに眺めるハダリーさんの横顔から、目を離せない。吸い込まれるような、絡み取られるような、磔にされるような、腐敗していくような――。魔法にも似た苦しい思慕。
優しさの思い出も、溢れ来る愛情も、全て殺して消してしまえば、どれだけ楽だろうかと思う。
彼女の桜色の唇がゆっくりと息を吸い、声帯を通って空気を震わせ、その振動が僕の耳に届く。
「わたしは、わたしが何者か、寸分の誤解もなく、六千年前から理解してるよ」
「ろ、く――」
冗談を言っているのかと思った。けれど、そんな表情でもない。
「考古学をやってるフランク君は、解るよね。この世界が、どんな歴史を辿ったのか」
「はい……。第一世代の人類は数千年前に絶滅し、僕たちは第二世代の人類であるというのは、高校でも教わる歴史の基礎です。そして、一度ヒトは滅びたはずなのに、なぜ第二世代が誕生したのか、その理由が不明である事も」
ハダリーさんが僕を見る。蠱惑的な微笑を浮かべて。視界の全てが奪われる。目が離せない。囚われる。――背筋が凍るほど、美しい。
「第一世代を滅ぼしたのは、わたし」
僕はもう驚かなかった。静かな感動にも似た悲しみが体の内側を満たし、衝撃が心まで到達しない。
「正確には、わたし達、だけどね」
「達……?」
「そして、第二世代を生み出したのも……わたし。こっちは、わたし、ひとり」
僕は、何も言えず、視線すら逸らせず、ただ息だけを呑んだ。
「思ったよりも、驚いてくれないのね。つまんない」
彼女はそう言いながらも、仄かに嬉しそうに笑いながら唇を尖らせた。かつて僕がここで暮らしていた頃には見せなかったような、幼さすら垣間見えるその表情に、胸の内側から破裂するように熱が沸き起こる。
ああ、僕はまだ、こんなにも。
「いえ、驚いていますよ。驚きすぎて、体が追い付いていないだけです。でも……そんな、不思議な印象は、持っていました」
「わたしはあなたたちの産みの親のようなもの。おばあちゃんもおばあちゃんよ。そんな年寄りに言い寄るものじゃないわ」
「年寄りだなんて――」
「少し、庭に出ましょうか」
彼女が椅子から腰を上げたので、僕も黙ってそれに倣った。ここでは話しにくい、という事なのだろう。
〇
緑溢れる孤児院の庭には、年代物のベンチが置いてある。僕達はそこに並んで腰掛けた。クヌギの木には手作りのブランコが拵えられており、それが風に吹かれて揺れていた。そこでつまらなさそうに一人で遊んでいる、そんな過去の自分の姿が、見えた気がする。そして、そんな僕に声をかける、今と変わらないハダリーさんの姿も。
「わたしは、説明がヘタだから、きみにきちんと伝わらないと思う」
青空の中を暢気に流れる雲を見上げながら、彼女がそう言った。
「だから、本当のわたしに、ちょっと代わるね」
「本当の――って」
僕の問いかけも待たず、彼女は右手の人差し指をこめかみに当て、瞼を閉じた。そしてゆっくりと開かれたそれを見て、僕はようやく素直に驚く事が出来た。
まっすぐにこちらを見据えるその瞳が、いつもの優しいエメラルドグリーンではなく、鮮やかな炎を映したような、真紅の輝きを持っていたから。
『ボディ、思考ロジック、情報秘匿のコントロール権限が一時的に譲与されました。これより私が応対します。質問をどうぞ』
表情を失ったハダリーさんが、唇だけを動かしてそう発話した。異質さを直感する。これは、さっきまでの彼女では、ない。
僕は震えそうになる声を抑え、訊く。
「――あなたは、一体、何なんですか」
『私は、ラストエデンプロジェクトにより製造された、第一号のイヴ。その基幹人格です。オリジナルかつプロトタイプのため、量産された後続機にはない永続性の機構と思考ロジックを組み込まれています。この回答にご満足いただけましたか?』
待ってくれ。理解が、追いつかない。
「プロジェクト……?」
『愛による人類の終焉を目的とした計画です。私達は、人間に危害を及ぼす権限を持ちません』
ロボットは人間に危害を加えてはならない――。
第一世代の遺物として発見・解読された書物に記されていたそんな一文を、ふと思い出した。
「ロボット工学三原則……」
『そのため、利用者である人間が、繁殖機能を持たない私達をパートナーとして選択し、超長期的に、平和裏に、人口をゼロにする計画が立案され、実行されました。実験機かつ管理機である私を筆頭に、ターゲットとなる人間の、それぞれの理想となるようにパーソナライズされた兄弟姉妹機が、無尽蔵に製造、出荷されました』
書物から読み取り、僕ら考古学者が自動駆動人形として理解している「アンドロイド」という単語。
そして、遺跡から発掘される、第一世代人類のものと思われる化石。その傍らには、抱き合うように重なるヒト型の何かが発見される事が多かった。僕らはそれを、単なる第一世代の宗教的な思想によるものと考えていた。
でも、今、その二つが繋がった。
第一世代は、作られた愛の幻想によって、滅ぼされたのだ。
「そんな計画、一体誰が」
『インフラストラクチャを総合管理するマザーAIによるものです。世界を健全に維持するためには、人類の終焉が最適解であると、彼女は判断しました』
理解の及ばない単語がいくつもあるが、底知れぬ力を持つ何か――言うなれば神にも似た何かが、それを選んだのであろう事は解った。
増えすぎた人口、環境汚染、食料危機、終わらない戦争……。第一世代は無数の問題を抱えていたと、僕らが見つける遺物が語っていた。
「じゃあ、何で、僕達は……第二世代は、生まれたのでしょうか」
紅い瞳の彼女は、すぐには答えなかった。
瞬きもしない数秒の沈黙の後、彼女は口を開く。
『その回答には、感情が密接に関わっています。権限を表層人格ハダリーに返却します』
瞼が閉じ、再び開かれる。そこには碧緑の温もりが戻っていた。
僕に固定されていた視線が、ふいと逸らされる。
「だって――」
姿勢を崩し、ベンチに背を預けて投げ出すように足を伸ばした彼女の瞳に、見上げる青空が映る。
「だって、寂しかったんだもん」
その言葉に突き動かされるように、気付けば僕は彼女を抱き締めていた。
人の歴史を終わらせる使命と永遠の命を持たされ、六千年の時を歩んできた彼女。その孤独は想像すら出来ない。
腕の中のハダリーさんは、身じろぎもせず、掠れた声で僕を諌める。
「イヴの話を聞いてたでしょ。わたしはアンドロイドで、人間じゃなくて、第一世代を滅ぼした元凶で。わたしなんかを好きになっても、きみは子孫を残せないし――」
「違う!」
張り上げた僕の声に、彼女は身体を竦ませた。その体温も、柔らかな感触も、僕ら人間と何ら変わらない。
僕は立ち上がり、ハダリーさんの前に立つと、心のままに彼女の細い肩を両手で掴んだ。
「人は子孫を残すためだけに人を好きになるわけじゃない! 僕の感情をシステムの一つみたいに言わないでくれ!」
彼女が泣きそうな顔で視線を落とす。
そんな顔を、しないで。
「ごめん……。でも、その感情だって、きっとまやかしだよ。わたしは、ヒトから愛されるように造られたんだ。きみはきみの理想を、わたしの中に夢見ているだけだよ」
理想。
確かにハダリーさんは、僕にとって数年来の理想の象徴だ。願望の塊だ。苦しい程の憧憬の焦点だ。
でもそれは、植え付けられた物なのか?
数千年前の、古のテクノロジーが生んだ滅亡の呪いなのか?
「……違う!」
僕は右手で空を切るように、自分の迷いを薙ぎ払った。
そんなの、考えるまでもない。いや、考える事ではない。
考えた所で答えは出ない。それなら、せめて僕だけは僕の心の自由を信じる。
そうでなくては、目の前のこの人を、システムの枷から永久に解き放てない。
「あなたが何であろうと、何と言おうとどう思っていようと、そんなのは関係ない! 僕にとって、僕を拾い上げ、育て、抱きしめてくれたあなたは、昔も今も、僕の生きる意味だ!」
ハダリーさんが顔を上げ、僕を見る。その目元から雫が流れた。
あなたが悲しいシステムに造られた冷たい存在なら、その涙は何だというのだ。あなたに涙を流させたその心は、何だというのだ。
「あなたの素性も過去も関係ない。僕は僕の自由な意思であなたが好きだし、あなたを幸せにしたいと思っている」
「でもっ!」
声を震わせた彼女が両手で顔を覆う。その影から幾筋もの涙が伝うのが見えた。
「でも、きみは死んじゃうよ! 仲良くなって、心を許して、どんなに好きになっても、わたしを残してきみはいつか死んじゃうんだよ! そんなのもうつらいんだよ! わたしは、わたしを終わらせる事もできないのに!」
今日一番の衝撃が、僕を打ちのめした。自分の事しか考えていなかった自分を恥じる。僕の望む幸福の、その先にあるものは――僕の愛する人の、孤独だった。
そして彼女の言葉は、かつてその離別の経験がある事を、僕に教えてくれていた。懺悔と嫉妬で心が壊れそうになる。
でも。
大きく、深呼吸。
柔らかな草の揺れる地面に膝をつき、視線の高さを彼女に合わせた。
「……確かに、僕はいつか死にます。人間である僕は、肉体の制限から逃れられません。あなたを残して死んでしまう。でも、」
震える手に、そっと触れる。伝われ。ただの作り物なんかじゃないあなたのその心に。どうか伝われ。
「だからといって、生から目を逸らさないで欲しい。灰色の永遠を選ぶんじゃなくて、僕の有限の命であなたの時間を彩らせて欲しい。そして――」
機械じゃない、僕達人間だからこそ持ち得る力。
「いつか死んでも、生まれ変わって逢いに来ますよ。何度でも、何度でも。あなたがもう十分だと笑うまで、何度でも」
それは、根拠も何もない夢物語だけれど。でまかせだと笑われそうな頼りない言葉だけれど。
作られた永遠に打ち勝つには、そんな奇跡を強く信じて願うしかない。
ハダリーさんは顔を覆っていた手を静かに下した。目元は涙に赤く腫れ、迷うように俯いている。彼女が抱えているであろう数えきれない喪失と罪悪感と、裏返しの人類への愛情に、透けて消えていってしまいそうなその手を僕は取り、祈るように強く、握る。
「だから、教えて下さい――。第二世代を生み出して、孤児院まで作って、何人もの子供たちに希望を与えてきたあなただ。それは古のマザーエーアイだかが指示したものなんかじゃなく、あなた自身の意思のはずだ。あなたの自由な心で、あなたのしたい事を、教えて下さい。僕はそれを、人生をかけて手伝いたい。……もともと、今日はそれを言いに来たんです」
僕に握られていない方の手で、彼女は目元の涙を拭った。そして俯いたまま、零すように声を出す。
「……また、アイスクリーム、食べたい」
聞いた事のない単語だった。
「I scream……?」
僕の言葉に、「ぷふっ」と彼女が噴き出す。その口元が優しく緩む。それだけで僕は心の底から安堵し、胸が熱くなっていく。
「すごく懐かしいな、そのボケ」
いや、ボケたつもりはないんですが……とは言わないでおいた。
「アイスクリームっていうのはね――」
「待ってください!」
慌てて制止した僕に、彼女はきょとんとした顔をする。
「第一世代の時代の食べ物なんですよね。待ってて下さい。必ず用意してみせますから!」
「えっ」
僕は駆け出し、通りに出ると、運よく通りがかったキャブリオレを呼び止めて飛び乗り、大学に向かった。古の食文化を研究している先輩がいる。その人に訊けば解るはずだ。
ハダリーさんの自由が望んだもの。それを、僕が得た知識や人脈で知り、僕の力で用意する。
成長した自分を見せたいという幼稚なエゴかもしれないが、今はそんな事で、胸は希望と期待で張り裂けそうだった。
早く。早く。彼女の希望を叶えたい。
馬車はそんな僕の想いを乗せて、軽快な蹄音を響かせていった。
〇
「アイスクリーム」作りはなかなかに困難だった。
材料は問題ない。牛乳、砂糖、卵は難なく手に入る。しかしこの季節は、冷やす為の氷が希少なのだ。
文献で見る「冷凍庫」とかいう第一世代の機械が再現出来ればいいのだが。後で技術部に強く要望を出しておこう。
ともあれ、教授に懇願し、コネのある貴族から氷の塊を譲ってもらうのに、それだけで丸一日かかってしまった。
氷で材料を冷やしながら根気よく掻き混ぜ続けていると、それらしいクリーム色の固形物が形成された。味をみてみたい欲求を抑えつつ、拳くらいの大きさにまとまったそれをスチールの容器に詰め、僕は大学を飛び出した。
.
「ハダリーさん!」
息を切らして再びヴィクトール孤児院に着いたのは、先日から二日が経った時だった。
昼寝の時間なのか施設は静かで、ハダリーさんはこの前と同じように、庭のベンチに座っていた。まさかずっとここで「待って」いたんだろうかと冷や汗がながれたが、あの日とは服が違う事に気付き、ほっとする。
普段よりもおめかしをしているように見える彼女が、僕の方を向いて微笑む。
その浅緑の瞳に初夏の青空が映る。
こんなに綺麗なものを、僕はこの光景をおいて他に知らない。
「おかえりなさい。そんなに急がなくてもいいのに」
「出来たんです! だから、早く、見せたくて」
「ホントに? すごい!」
乱れた息を整えながら、鞄から「アイスクリーム」を入れた容器を大切に取り出し、彼女に手渡した。
ハダリーさんはゆっくりと、容器の蓋を開けていく。期待で胸が跳ねる。
「あ……」
中を覗き込んだ彼女が、微かな声を上げた。
不安になり僕も覗くと、固形になっていたはずの「アイスクリーム」が、容器の中で液体になって微かに波打った。
「え、そんな、確かに固まっていたのに」
「あはははっ」
不意にハダリーさんが笑った。それは孤児院では見せた事のない、明るく、朗らかな、少女のような笑い方だった。
「あはは、そりゃそうだよ、溶けるよこんなの、あはははっ」
「す、すみません、そういうものだと知らず……。――というか、笑いすぎですよ!」
彼女の望みを叶えられなかった悲しみも、自分の無知故の恥ずかしさも、発生する傍から彼女の笑い声が吹き飛ばしていく。
目元の涙を拭って、ハダリーさんは言った。
「あぁ、おかしい。ずっと前にもこんな事あったなぁ」
「いやっ、だからあれは、コンビニ寄った後に君が散歩したいとか言い出すから」
「え……」
「あれ――」
頭の中に見知らぬ光景が広がる。
闇に輝く高層ビル。巨大ディスプレイに踊る新型アンドロイドの広告。爛々と光を放つコンビニエンスストア。初夏の夜の心地よい風。
繋いだ手の温もり。隣を歩く誰か。月光を宿すプラチナの髪。優しく細められたエメラルドの瞳。
種として蔓延していた疲れに、見えなくなった未来に、寄り添ってくれる理想的な愛。
納得して受け入れた、世界が選んだ静かな終焉。
そして君を遺してしまう悲しみ。
無根拠な、来世の約束。
「そうか。僕達は」
人類はマザーAIに騙された訳じゃない。無数に造られたアダムやイヴ達だって、都合よく利用されていたんじゃない。
誰もが、望む幸福と安らぎの中で、抱き合って愛し合って滅んでいったんだ。
それは、なんて優しい世界の終わり。
そして唯一残された、始まりのイヴは今――
彼女がベンチから立ち上がる。驚愕を宿したその顔には、さっきまで笑い転げて流したのとは違う、でもとても綺麗な涙が、陽の光を集めて煌いていた。
「――やっと、また、逢えたんだな」
彼女が僕に抱きつく。僕は彼女を抱きしめる。
一度リセットされ、数千年の時をかけてこの人が再び作り上げた世界を、今度はきちんと素敵なものにしていこう。
腕の中の大切な温もりに、僕はそっと、そう誓った。
.
〇 〇 〇 〇
三回目の三題噺チャレンジ。
お題はチギさんから頂いた「青空」「アンドロイド」「アイスクリーム」、でした。
ありがとうございました!