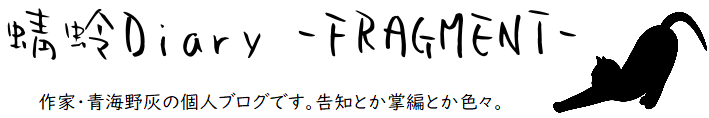想いは、呪いに似ている。
「先生、そっち歪んでますよ」
「え、そうか?」
ゆるゆると気だるげに粉雪が降る。それに逆らうように、彼の吐く息が白く烟って灰色の空に立ち昇っていく。
「……先生、雪だるま下手ですね」
「……それ、初めて言われた」
「私も初めて言いました」
誰もいないグラウンドには、辺りに人の気配もなく、町に満ちるあらゆる騒音が雪によって隠されて、私たちの呼吸の音だけが繰り返し響いていた。まるで、ここにいる二人だけを残して、世界がひっそりと終わってしまったのではないかと感じるほど、静寂と、白が、全てを埋めつくしている。
そうだったらいいのに、と、私は思う。
私と彼だけを遺して、世界が終わってくれていたらいいのに。
「こんな事するの、十年以上ぶりだからな」
「私は人生で初めてですよ、こんな事するの」
「え、そうなのか。にしては手際がいいな」
予習しましたから、とは言わなかった。
高校のクラスに馴染めずに保健室登校をしていた私に、体育の授業の替わりとして与えられた課題が、この「雪だるま作り」だった。初めに聞いた時は、それが17歳の人間にやらせる事かと耳を疑ったけど、監督の教師の名を知らされて、私の胸は複雑に軋んだ。
「それにしても、」
先生はひとつ大きな息を吐いて、コートの袖で額に浮かんだ汗を拭う。
「思った以上の運動量だなこれは。最初に話を聞いた時は高校生を馬鹿にしてるのかと思ったけど、なるほど体力作りにはもってこいの作業だ」
寒さのおかげか汗は出てないけれど、私の息も切れている。雪の積もった場所を歩くだけでも疲れるというのに、雪玉を押し転がして大きくする作業は、普段から運動に縁のない私にはただの苦行だ。監督が彼でなかったら、私は今日、体調を崩して休んでいたことだろう。
「じゃあ、乗せてみるかい?」
「そうですね」
私たちの前には、それぞれの腰ほどの高さにまで膨らんだ雪玉が二つ、並んでいる。私が作った小さい方を、彼が作った大きい方の上に乗せれば、ひとまずは雪だるまの体をなす。そこに、目や鼻、腕や帽子などのデコレーションを加えれば、完成するはずだ。
二人で雪玉の前に立ち、腰を屈め、玉の重心より下に両手を添える。コート越しに、腕が当たる。彼にかつて触れられた身体が、熱を持っていく。胸が苦しく暴れる。
「上げるぞ」
そう言って力を入れた彼のコートの袖と、革の手袋との隙間に、薄い肌の色が覗く。そこに、艶やかな黒が巻き付いているのが見えた。腕時計でも、ブレスレットでもない。私はそれが何かを知っている。
体の力が抜けていく。
心が冷たく凍えていく。
「よっ」
玉を持ち上げて二つに重ね終えた彼が、後ろで一人佇む私を振り向いて笑った。
「ひどいな、僕一人にやらせるなんて」
「先生」
「ん?」
何も分かってない微笑みで、私を見る。
「私を、殺して下さい」
彼が悲しげな顔をする。私はどんな顔をしているだろう。
「それは出来ないと、前も言っただろう」
「じゃあ、」
頬がひりひりと痛み出す。寒さのせいか、こらえている涙のせいか。
「それ、切って棄てて下さい」
彼の左手を指さしながら言った声は、震えてしまった。
先生は私が指した先を見て、私を見て、小さく首を振る。
「それも、出来ない」
彼が左手首に巻いている黒いミサンガが何で出来ているか、私は知っている。
想いは、呪いに似ている。
「じゃあ、夏休みにあなたが私にした事を、校長に話します」
深く吐き出された彼の息が、白くなって空に消えていく。冬のあの重そうな雲は、きっと人々の溜め息の集合体なんだろう。
「あの時の事は、本当に、すまないと思ってる」
彼は小さく頭を下げた。そんな事で私の心は変わらない事も、脅迫めいた私の言葉で彼の心が変わらない事も、悲しいくらいに分かっていた。本当は思い止まれた彼に、寂しさの腕を伸ばして引き込んだ私が悪いという事も。
「……とりあえず、完成させてしまおう」
彼が話を切り替えた事を、ありがたいと思った。私はうなずき、何事もなかったように彼の隣に立つ。
「顔はどうするんですか?」
「実は、百円ショップで色々用意してきたんだ」
そう言うと先生は、傍らに置いてあった紙袋から様々な物を取り出してみせた。大きな黒いボタンや、毛糸の手袋や帽子、「これは外で拾ったんだけど」と、木の枝も出てきた。
私はくすくすと笑いながら、「準備がいいんですね」と言った。
「先生、何気に、楽しみにしてたんですか?」
「そうだね、楽しみだったよ」
彼は無邪気に笑う。胸が掴まれるように痛む。
「それは、この作業がですか?」
「え?」
「それとも、私と遊ぶことが、ですか?」
自分は面倒臭い女だな、と思う。彼の奥さんは、きっともっと素敵な大人の女性で、こんな事は言わなかっただろう。
先生は少し私の顔を見たあと、優しく微笑んで「そうだよ」とだけ言った。
この人はずるい大人だと思う。死んでしまえばいいのに、と思う。
私にかけられた呪いが深まる。
❄
「いいね」
「いいですね」
私たちは手袋についた雪を払って、完成したそれを並んで眺めた。
ボタンの目と、プラスチックのニンジンの鼻、枯れ枝の口。赤い毛糸の帽子と手袋。余ったボタンは胸元に三つ、縦に並んでいる。
頭部に対して胴体がやや歪な形だけれど、先生が用意した小道具のおかげで、雪だるまはかなりかわいいものが出来上がった。いつか溶けてなくなってしまうのがもったいないと感じるほど。でも、V字に並べた枝で口元に笑みを浮かべているはずの雪だるまは、なぜだか少し、寂しそうにも見えた。
「じゃあひとまずこれで、君の体育の課題は完了だ。お疲れ様」
「はい、ありがとうござました」
「葉月さん」
唐突に彼が、私の名を呼んだ。
「はい」
「僕を、殺してくれ」
本来忌避すべきはずの死を望む生物は、人間だけなのだろうか。
「……それは出来ないって、前にも言ったじゃないですか」
「そうか。そうだよな。僕が出来ない事を、人に望んじゃいけないな」
「そうですよ」
彼は疲れたような声で笑った。
授業の終了を告げるチャイムが鳴る。今日で、二学期が終わる。冬休みが始まれば、学校で先生に会えなくなる。
でも、また、彼のマンションに遊びに行けばいいか、と私は楽観視していた。
「じゃあ、僕は戻るよ。葉月さんもゆっくり休んで、風邪ひかないように暖かくしてね」
「はい」
先生は小さく手を振ったあと、グラウンドの雪原を踏みしめて、校舎に向かい歩いていく。私は彼と作った雪だるまの隣に立ったまま、その後姿をいつまでも眺めていた。もし、足を止めて振り返って私を見てくれたら、駆け寄って抱きしめよう。そう思っていても、先生は振り返らなかった。
――泣き疲れていた彼が、泣き疲れていた私を抱いた、あの夏の日。
その翌朝、白い光と鳥たちの囀りの中で、自分が幸せになる事を禁じる呪いを課すように、彼は奥さんの遺髪で編み上げた黒いミサンガを、左手首に巻いた。
――そして、二人で息を切らして雪だるまを作った、この冬の日。
その翌朝、先生は厳冬の深く昏く冷たい海に、身を投げた。
❄
柔らかなオレンジ色の照明の下で、てのひら大のスノードームが、中に舞う粉雪をゆらゆらと輝かせている。
「綺麗ですね、これ」
熱帯夜でもエアコンが吐き出す空気で部屋は涼しく、ドームの中央で笑顔を見せる小さな雪だるまを眺めていると、私の心には冬の冷たい風が、心地よく吹き込んでくるように感じられた。
「ん? ああ、」
私の声に、まどろみかけていた彼がベッドから身を起こす。
「綺麗だろう。ロンドンのお土産だよ」
「これ、私に下さい」
この時の私は、先生の所有する物を何でもいいから持っていたかった。それだけで縋り付く物を得る私は、暫くは生きていけそうな気がしたのだ。
「ダメだよ」
彼は優しく笑う。
「大事なものなんだ」
「私よりもですか?」
私は私の命と寂しさを人質に、いじわるな質問をする。けれど先生は揺らがずに、
「そうだよ」
そう微笑んで言いながら、私の頭にそっと手を置いた。奥さんの思い出なんだろうな、と、私は思う。
この時の彼の手首にはまだ、ミサンガは巻かれていなかった。
❄
ザク、ザク、ザク、と靴が音を立てる。
グラウンドに積もった雪は夜中の冷気に硬く凍り、踏む度に砕けるような感触を足に伝えた。
私は息を切らしながら、まだ残っている雪だるまの元に、一人辿り着く。冬休みが終わるこの日は、ちょうど私の誕生日だ。日付と時間帯の指定付きで昨日の夜に届けられた先生からの手紙に、こう書いてあった。
「君の誕生日に、あの雪だるまを砕いて解き放ってくれ」、とだけ。
私は誰にも見つからないように夜中に目覚ましで起き、家をこっそり抜け出してここまで来た。乱れた吐息が、白い月夜に浮かんで消える。
西暦が変わっても雪だるまは溶けてはいなかったけれど、手袋は落ち、片目は剥がれ、口もV字の片側だけになり、堪えきれない孤独に顔を歪めているように見える。もしかしたらこれは、私の半身なのかもしれない。
「もう、楽にしてあげるよ」
家から持ってきたスコップを振りかざし、寂しさの化身みたいに佇む雪だるまに突き立てる。私が作り、先生が重ねた頭部は、たった一度の衝撃で地面に崩れ落ちた。足元に転がったボタンの瞳が、私を見上げて何かを訴える。でも私の心は、それを掬い取る余裕がない。
冷たい空気を吸い込んで再度スコップを振り上げると、今度は胴体に突き刺した。固くなっているそれはひとつの破片になっただけで、原形を留めている。私は何度も、何度も、スコップを振り下ろした。未練の糸を断ち切るように。想いの欠片を、砕くように。
胴体が半分ほどになった時、雪の塊の中央に箱のようなものが見えた。周りの雪を削って取り出すと、それは両手に乗るくらいの白い小さなダンボール箱だった。
先生が私に雪だるまを砕かせた意図は、きっと、これなんだろう。ということは、あの日、私と雪玉を転がしながら、彼は既に自分がいなくなる世界を見つめていたのかもしれない。
スコップを放って、手袋を外して、私は箱を開けた。中には折り畳まれた紙と――
「ああ……」
彼のマンションのベッドルームに飾られていた、雪だるまのスノードームが入っていた。
「いまさら、こんなもの、くれたって……」
いつの間にか辺りは、夜明けの静謐な光が漂い出している。私はドームを静かに足元に置き、雪の上に膝をつくと、四つ折りにされた紙を丁寧に広げた。
『僕の妻が、僕ではない男の後を追うように身を投げた時から、
僕は自身の存在する理由や意欲を失っていった。
あの夏の日、君の存在に救われていたのは本当だ。
あの日以降、僕の半分は、君の為に生き残って、
君の為に存続していたと言える。
でももう半分は真っ黒に塗り潰されていて、
それは少しずつ、残された片方を侵食していくんだ。
君に求められる事は甘すぎる歓喜だ。
でもそれは、あるべき形の愛ではないと思う。
僕は君に寄りかかってしまったけれど、
君は僕に依存すべきではない。
君は僕から離れ、眩い未来を歩む権利と義務がある。
さようなら、ありがとう、僕を救おうとしてくれた人よ。
そして、誕生日おめでとう。』
「うあぁ……」
体が震え、涙がぼろぼろと零れて止まらない。私は夜明け前の仄暗い空に叫んだ。
「ああああぁ!」
想いは、呪いに似ている。
私に救われたと言ってくれる彼が、私を救ってくれていた事を、彼はどれだけ知っていただろうか。そしてこんな幕引きが、楔にしかならないという事を、彼はどれだけ考えてくれただろうか。
どんな夜にも、残酷に太陽は昇る。校舎の陰から朝焼けが赤い光を放ち、ぼろぼろになった雪だるまと、ぼろぼろになった私と、先生のスノードームを照らし出した。ドームの中の雪だるまは変わらずに幸せそうな笑顔で、朝日を受けてキラキラと輝く粉雪に囲まれている。
私は涙を拭い、そして決意した。
コートのポケットから黒いミサンガを取り出し、今だ艶を失わないそれを、丁寧に解いていく。
❄
数日ぶりに訪れた病室のベッドの上で、彼はぼんやりと窓の外を眺めていた。
私が近付くと、数秒間私の顔を眺めたあと、申し訳なさそうに眉を下げた。
「すみません、記憶がなくて……、知り合いの顔も名前も、覚えていないんです」
医師は、心因と外傷の両方を起因とした逆行性健忘、と言っていた。要するに、記憶喪失だ。彼の自殺は失敗していた。岩場に打ち上げられていた彼が病院に運ばれたのは、彼が海に飛び込んだ二日後。噂を聞きつけ駆け付けた私は、ベッドで昏睡する彼の傍に置かれていた黒いミサンガを、そっとポケットに忍ばせ、その場を去った。彼の知らない所でこの呪いを処分してしまおうと、そして自分も彼の世界から消えてしまおうと、その時の私は思っていた。
「私は――」
彼は失敗した。でも彼が望んだ結末の失敗は、彼にとっても、私にとっても、きっと成功に限りなく近い、幸福な喪失なのだろう。
「私はあなたの、恋人なんですよ」
「そうなんですか」
少し目を丸くした彼に微笑み、私はベッドに腰を下ろす。
「こんなに綺麗な人が恋人だなんて、僕は幸せな人生を歩んでいたようですね。早く思い出さないと」
「そうですよ。あなたは幸せだったんです。でも、無理に思い出さなくていいんですよ。過去なんてなくしてしまっても、あなたはこれからも、ずっと幸せなんですから」
彼が悲しみに震えるなら、私は嘘を折り重ねた毛布で、いつまでも温めよう。
彼は優しく微笑み、「ありがとう」と言う。
そして、私の髪に編み込んだ、過去の先生の奥さんの遺髪を、その優しい指先でそっと撫でた。
想いは、救いに似ている。
❄ ❄ ❄ ❄ ❄
二回目の三題噺チャレンジ。
お題は桜まくらさんから頂いた「雪だるま」「夜明け」「ミサンガ」、でした。
ありがとうございました!