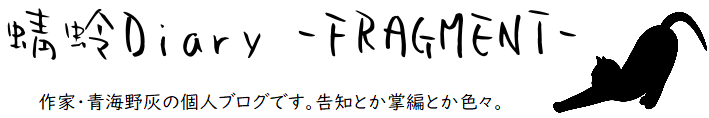お題:ラーメン
三分が経ちフタを開けようとすると、目に見えない温もりにその手を止められる。僕の手に触れる安らぎの感触の中に、妙な強い意思を感じる。
「いつも思うんだけど、気に入らないならもっと早くに止めてくれないかな。お湯を入れる前とか、コンビニで買う時とかさ」
そう出来ない事は分かっていて悪戯っぽく言ったが、当然返事はない。だが僕の手を止める力が緩められる気配もない。
「ああもう、分かったよ。ちゃんとしたもの買いに行くから、とりあえず離してくれ」
温もりは躊躇いがちにそっと僕の手を離れ、代わりに背中に感触が置かれた。じんわりといつもの温度が服を通して背に伝わる。
手が開放された事で、カップのフタが自然と捲れ、白い湯気と共にチープだが魅惑的な香りが溢れて鼻腔をくすぐる。音を立てないようにフタをはがし、そっと箸を持って静かに麺をすくい、口元に運んで一気にズルズルと啜った。途端に僕の頭がポカポカと叩かれる。
「あははっ、冗談だって、ごめんごめん。これ一口だけだから、やめろよ、ははっ」
こんな風にして君は、いつも僕の楽しみのジャマをする。けれどそのやりとりは、これから流しに捨てられる即席麺なんかより、よほど温かい。
透明な温もりと手を繋いで、近所のスーパーへ歩いた。僕の下らない話に、君が小刻みに手を握って笑っている事を伝える。傍から見たら僕は、独り言の多いさぞや怪しい男だろう。
カゴに材料を入れてレジに向かうと、そこにいた店員に名前を呼ばれた。
「修一さん」
今年大学生になった美穂ちゃんが、笑顔で手を振っていた。僕の右手を握る君の手の力が、少し強くなった気がした。
「野菜炒めですか? 言ってくれればいつでも私が作るのに。……奥さん亡くなってから、大変でしょう?」
「君にはあの時十分過ぎるくらい世話になって感謝してるけど、僕もいい加減自立しないといけないからね」
「……やっぱり、未来よりも過去の方が大事ですか? 生きてあなたを愛してる人が、すぐ近くにいるかもしれないのに」
僕が何も言えないでいると、彼女は商品を読み込む手を止めて、上目遣いで僕を見た。その瞳の潤んだ輝きにズキリと胸が疼くと、右手がキリキリと痛いくらいに握られた。
「ちょ、ちょっと、手離してよ、財布出せないだろ」
そう囁くと、君の温もりはそっと離れた。
会計と袋詰めを終え、右手を空中に差し出したが、それを掴む手はなかった。そのまま暫くスーパーを歩き回っても、僕の右手は何の温もりも捉えない。
「修一さんどうしたんですか? 挙動不審ですよぉ」
「あ、いや、何でもないよ。じゃあまたね美穂ちゃん」
彼女の声に慌てて店を出て、入口の前で右手を差し出していても、行き交う客に奇異の目で見られるだけだった。
視力を失った君が一人で先に帰っているはずはないと知りながら、強く願う様にノブを握って家のドアを開けても、抜け殻のような空気が満ちているだけ。
「おい、怒ってるのか?」
呼びかけても、謝っても、懇願しても、泣き喚いて町中を走り回っても、君の温もりは戻らなかった。
あれから時が経ち、相変わらず一人の僕は、それを止めてくれる手を求めて、毎日カップ麺ばかり食べていた。君に隠れて食べる時はあんなに旨かったのに、今は濃い科学的な味がビリビリと舌を刺激するだけで、苦痛でしかない。
あの痛いくらいに握った手は、お別れのサインのつもりだったんだろう。どうせ君のことだから、自分が消える事が僕の幸福に繋がるとでも思ったのだろう。でもそれは大間違いだ。君は僕の想いの強さを知らないのか。このままでは僕は、栄養失調で死んでしまうぞ。それでもいいのか君は。
ある日クタクタになって仕事から帰ると、机の上で丼のラーメンが湯気を立てていた。野菜が沢山入って中央にトマトが鎮座する、僕の好物の、生前の君がよく作ってくれた塩ラーメンだ。
呆然としていると、エプロンを付けた美穂ちゃんがおずおずと出てきた。
「修一さん、勝手に入ってごめんなさい……」
「おい、僕の妻を見なかったか! いや、見えなくても、何か感じなかったか!」
掴みかかった僕に、美穂ちゃんは申し訳なさそうに俯いて、一枚の紙を差し出した。
そこには、子供が書いたような乱れた字で、ラーメンのレシピと、「修一をおねがいします」とだけ書かれていた。その文字が涙で滲まないように、僕はすぐにそれを彼女に返した。
まったく、君は、最後の最後まで、人の事しか考えないんだな。
「あ、あの、伸びないうちに、食べて下さい」
そう促がされて啜ったラーメンは、間違いなく君の味と温もりを宿していて、僕は格好悪く泣いて呻きながら、止まらない感謝と共に、涙まみれの麺を咀嚼した。