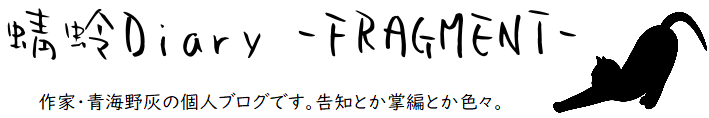お題:結婚
奏花は笑顔だった。それでいいんだと思う。
クチナシの花を配した純白のドレスに包まれ、皆から祝福されている姿を見ると、僕の胸に空いた穴が少しだけ塞がる様な気がした。
大きなガラス窓から六月の海が見える、白を基調とした式場で行われた結婚式は、参列者も大満足のようだった。
その後の空色のログハウス風披露宴会場も好評で、密かに式場選びに付き合わされていた僕も、肩の荷が下りた心地だった。
新郎は未だ緊張の抜けない表情で、友人からビールやらをグラスに注がれている。あいつの人の良さは、僕はもう十分に知っている。あいつなら、奏花を幸せに出来るだろう。
それでいいだろう。ずっとそれを望んでいただろう。でも心は、今にも壊れそうだった。
◆
十年前、僕達が高校生だった頃、奏花は僕の子を身籠った。
彼女は電車で4時間の地に住む一つ年上の従姉で、木漏れ陽の良く似合う綺麗な人だった。
互いに欠落した境遇にいた僕達は、逢う度に吸着するように惹かれ合い、夢中で寂しさを触れさせ合った。彼女に包まれている時だけが、生きている事を実感出来る瞬間だった。
僕達は遠からず結婚し、授かった子供を育てるつもりだったが、奏花は僕の知らない所で、猛反対した親戚達により半ば強制的に堕胎させられ、療養と称して僕の手の届かない遠くの地に移転させられた。
それを知った夜、苦しさにベッドの中で呻き、血が出るまで頭や顔を掻き毟り叫びながら、彼女の無事を切願した。
眠れないその祈りは、彼女が移転先の町の林で首を吊ったと聞かされるまで、止む事はなかった。
幸い彼女は一命を取り留め、ひと月後に病院のベッドで意識を取り戻した。
ただ、腕に点滴の管を繋げたまま僕の顔を見上げて
「三途の川に浸って霊感が付いたかも」
と冗談めかして微笑む奏花が無理をしている事は、明らかだった。
僕の前では彼女は素直に笑えなくなっていて、僕ではもう、彼女を幸せにする事は出来なかった。
◆
だから今日の日は、僕が待ち望んだ事なんだ。奏花が心から笑い、幸せになる日だ。僕もそれを喜ぶべきなんだ。
友人達の余興で盛り上がる披露宴会場から一人抜け出し、クチナシの白い花が咲き誇る芝生の小丘の上でぼんやりと海を眺めた。やがて会場の青い扉が開き、そこから花嫁が一人出てきた事には驚いた。
――主役が不在になっていいのかよ。
「今はお色直し時間でね、ちょっと抜け出してきた。涼こそ勝手にどっか行かないでよね」
奏花は僕の横に立ち、僕と同じように海を見た。木漏れ陽が彼女に当たって揺れる。
「いい式場だよね、すごく綺麗で、皆喜んでくれて、私も嬉しいよ」
彼女がそう言い、ドレスに包まれたお腹に手を当てたので、僕はすぐに目を逸らす。そこには、夫との待望の子がいるらしい。
その現実と、着飾った彼女の眩さが、ビシビシと僕の心をヒビ割れさせていく。
奏花の幸福を何よりも願っているのに、そのヒビの奥で蠢く黒く淀んだ感情は、醜く歯痒く苦しい、嫉妬だ。
――……僕のものにならないのなら、さっさと死んでくれないかな。
「またそんな冗談を言う」
口を衝いて出た心にもない言葉を、奏花はさらりと受け流した。
そしてきっと彼女は、僕のこんな感情をも見抜いている。
暫しの沈黙、そして、
「あの地獄の様な日々の中、間違いなく、私はあなたを愛していました」
――なんで急に、敬語なんだよ。
「私は幸せになりますから」
――だからなんで
「もう、大丈夫だから」
震えが交じった声に振り向くと、奏花は泣いていた。笑顔のまま、大粒の涙を流していた。
「ずっと傍にいてくれてありがとう。心配してくれてありがとう」
僕の方を向き、頭を下げる。伝った涙が鼻先や顎からぽたぽたと落ち、ドレスを濡らていく。
――おいやめろ、見つかったら変に思われるぞ。
他人からしたら、ドレス姿の花嫁が虚空に向かって頭を下げる光景に見える事は、僕も知っていた。
「だから、もうっ」
あの日、奏花が首を吊ったと聞かされた日。
僕も後を追う様に首を括らなければ、今日彼女の隣で祝福を受けるのは自分だったのだろうかと、今でも思う。
「涼も、自由になって下さいっ…」
さよならの覚悟に、僕を縛っていた嫉妬が、静かに霧散していく。
出来る事なら僕の手で、君を幸せにしたかった。それは今でも変わらない。
でも君がもう、大丈夫だと言うのなら、僕がここにいる理由は、もうない。
――……分かった。
僕は僕の意思でこの呪いを解き、僕の体は風になった。今となっては、それは簡単な事だった。
彼女の頬を撫でると、涙が風に交じった。六月の海風が、クチナシの匂いと共に僕を空へと吹き上げていく。
「さよなら……さよなら! 絶対に幸せになるから!」
奏花は笑顔だった。誰よりも幸せそうだった。だからそれでいいんだと、思う。