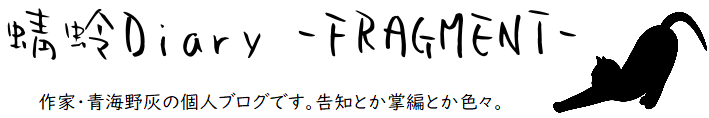※こちら↓を先に読んで頂いた方が楽しめるかと思いますが、強制はしません。
『世界の終わりを君と』
☁ ☁ ☁
二人で、錆び付いた鉄道のレールの上を歩いた。
かつて世界を遍く満たし、そこにあった全ての業や咎、あらゆる絶望や悲劇を洗い流した水は、今も僕らの足元で波も立てずに、透き通る青空を一面に反射している。そこに線路の上部だけが辛うじて顔を出して、水平線の先にまでまっすぐに伸びているものだから、まるで空の中を歩いているような気分になる。
いつかは、この星を覆う水も引いていくのだろうか。太陽に照らされて、少しずつ蒸発して。または、広大な大地に少しずつ浸透して。あるいは、これを呼び起こした何らかの意思の大いなるチカラによって、一夜のうちに。
いずれにせよ、その未来が訪れるのであればそれは少し寂しいな、と僕は思う。もう幾日もの時間を、君と二人で水と共に過ごしてきたから、僕はもうすっかり愛し始めているんだ。この、奇跡のような光景を。
「銀河鉄道みたいだよね。見たことないけどさ」と、僕の前を歩く君が楽しげに言う。
その気持ちも分からないでもないけど、その言葉は夜になってからもう一回言ってくれる?
「え、なんで?」
銀河というものは黒が満たしているんだ。静かに冷たい、何物をも飲み込む黒が、優しく覆っている舞台なんだよ。そこに砂粒みたいだったり、金平糖みたいだったりする星々が、無数に散りばめられている。
それはこんな快晴の青の中よりも、夜の時間の方が似合うセリフだし、僕も心から同意できると思う。ああ、そうか、夜というものは、銀河の眷属なのかもしれないね。
前を歩く君は「ふふ」と小さく笑い、
「相変わらず君は小難しく考えるなぁ。青と白の銀河があったっていいじゃない」
そう言うと、空に浮かぶ雲にも似た純白の翼を横に大きく広げて歩きながら、優しくつやめく嘴で、聴き覚えのあるようなメロディーを紡ぎ出した。
君の歌はいつも、僕の心を綻ばせ、ともするとそこに忍び寄る暗雲を、いとも容易く吹き払ってくれる。
僕は聴き惚れて落ちてしまわないように、脚の爪でしっかりとレールの縁を掴んで、君を追いかけて歩く。飛べばいいじゃないか、なんて無粋なことは、今は言わない。
それ、何の曲だっけ?
「知らなーい。適当に歌ってるだけ」
君はそう答えたあと、適当なメロディに乗せて歌うように言葉を続ける。
「私たちはあの頃みたいに、手を繋げなくなったけど」
あの頃、まだ人間の形をしていた僕たちは、今みたいに水浸しの世界の上を、二人で手を繋いで歩いた。不思議とその記憶は、この小さな身体にも残っている。
「でも私、この世界が好きだよ」
それは僕も同意だ。
「羽で触れ合えるし、嘴でキスもできるし」
木の実は美味しいし。
「急にロマンがないけど完全同意」
君は僕の方を向いて一度頷いた後、再び歩き出す。
「神様みたいなのが本当にいるのかは今でも分からないけど、それはきっと、とても優しくて、弱い存在なんだと思う」
弱い? というと?
「弱さを持ってないと、優しくあれないよ。きっととても傷付きやすくて、泣いたり笑ったりする、私たちとそんなに変わらない存在なんじゃないかな」
なるほど、そうかもしれないね。僕たちの魂や意思のようなものをどこかにプールしておいて、こうして再利用して、また逢わせてくれたんだ。その行為には弱さを知る優しさが滲んでいる。
「プールするって何?」
貯めておくってこと。
「ふうん」
……でも、こうして再び命を与えられた僕たちは、いつか――
「ん?」
……いや、なんでもない。
咄嗟に嘴を噤んだ。ついネガティブな方向に考えてしまうかつての僕の癖も、この身体は受け継いでしまったようだ。
僕たちは今、生きている。かつて取り残された約束が世界に零した、残滓のような在り方であったあの頃とは違う。
命は光であるとは思う。炎にも似ている。今の僕の肉体は、世界に正しく影を落とす。けれど、その光は、いつか燃え尽きる。
やがて僕は死ぬし、それは、君も例外ではない。
僕を残して君がいつか死んでしまう、あるいは、いつか死ぬ僕が君を残してしまう。そんな避けられない未来を思うと、こんな眩く美しい景色の中であっても、僕の心は暗い雲に覆われていく。
だから僕は、君に告げる。
ねえ、また歌ってよ。
「おっけー。私歌うの好きだよ」
前を歩く君の歌声で心の雨雲を晴らしながら、僕は精一杯の幸福な未来を夢見て、嘴を開き、囀る。
いつか最期に眠る時も、君と一緒だといいな。
「もしかしてそれって最上級の愛のことば?」
そうだよ。
臆面もなく素直にそう返すと、君は照れたのかその柔らかな翼で顔を隠すように覆った。その向こうから、小さな囀りが聞こえる。
「いつか二人で死んじゃっても、またこうして生まれ変わって、逢えるといいね」
僕は小さく息を呑んだ。
そうか、この世界には。全ての悲しみを洗い流した、弱くて優しい神様がいる。それなら、そんな未来も、あるのかもしれない。それが示唆する輪廻の可能性は、途方もない救済と、命の閉塞感からの解放を僕にもたらす。
やはり、君がいるこの世界は、とても優しい。そう思う。
僕は嘴を開いて澄んだ空気を胸に取り込み、君に向けて喉の奥を鳴らした。
それはもしかして、最上級の愛のことばなのかな?
「知らなーい」
君は嬉しそうにそう言うと、前を向いて再び歩き出した。
風が通ったような軽やかな心で、僕もそれに続こうと脚を出した時――
ガチャン、と金属の柵が開くような音がして、僕の身体はびくんと硬直した。
「あ、人が来ちゃったね」と君が言う。
「そうだね」と僕はうなずく。
「じゃあ、今日の『世界の終わりを君と』ごっこはここまでだ」
「え、今日の、ってことは明日もまだやるの?」
「そうだよ。楽しいじゃん。君は楽しくない?」
「……いや、なかなか詩的で恣意的な遊びだったと思う。素敵だよ」
「よかった。じゃあ今日は帰ろう!」
そう言うと君は羽ばたき、いくつかの白い羽根を残して空に舞い上がった。
その光景を見て僕は、まるで自由の雲みたいだな、と思った。
☁
「あ、見て見て、鳥がいるよ!」
水着姿の友人が指さす先を見ると、私たちがこれから部活で入るプールの水面、その真ん中辺りのコースロープの上に、片手の中に納まりそうなくらいのサイズの一羽の鳥が立っていた。青い空の色をそのまま絵の具にして塗ったような綺麗なセレストブルーの身体で、逃げもせずにじっと私たちの方を見ている。
「かわいいねえ、水浴びしてたのかな。けっこう小さい種類だね」
「キンカチョウ、かな」と私は言う。
「へえ、よく分かるね」
「前に飼ってたことがあるんだ」
ふと空の方から鳥の鳴き声が聞こえ、私たちは上を向いた。眩しい太陽の光のそばで、同じ種類なのか小さな身体の白い鳥がホバリングしていて、下の鳥を呼ぶように、ちちちと鳴いている。
すぐに羽ばたきの音がして、さっきの青い鳥が、白い鳥のもとまで飛び上がったのが見えた。二羽はしばらくじゃれ合うように空中で踊った後、軽やかに鳴きながら遠くの空の方に飛んで行った。
「鳥の鳴き声って、ちょっと歌みたいだよね」と友人が言う。
「実際、キンカチョウは歌を歌うんだよ」
「え、そうなの?」
「そう。求愛の歌を歌うんだ」
「ふうん。さっきの二羽、恋人なのかな」
「そうかもね」
私たちはしばらく、柔らかな白雲を抱えた青空を、ぼんやり見上げていた。
「さ、練習練習!」
そう言って私の背を叩き歩き出した友人の後を追い、私も前を向く。
初夏の陽光を優しく乱反射するプールの水面は、いつもよりも少し、綺麗に見えた。
☁ ☁ ☁
四回目の三題噺チャレンジ。
お題はマシュマロで頂いた「歌」「線路」「プール」、でした。
ありがとうございました!