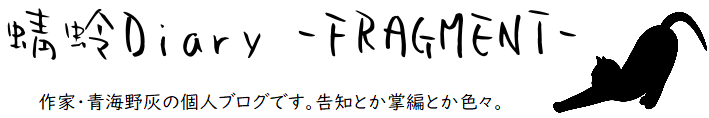昨日は爽やかな青空が広がっていたのに、今日はまた雨空。でもその肌寒さも、秋の到来を感じて嬉しい。(夕方くらいにまた晴れたけど)
*
今日は普通に仕事の日だけど、髪が伸びて邪魔になってきていたので、途中で髪を切りました。
(仕事の話とその悩みについてはまた別の日記にしよう)
僕は、美容室とか床屋というものに全然行ってません。髪はいつも自分で切ってます。
美容室に行ったことは何度かあるんだけど、美容師さんと世間話をしたりするのが苦痛で苦手なんですよね。
(悲しいくらいの社交性の無さ。いや、ノリの良さを演じることはできるけど、めちゃくちゃ疲れるんですよ)
自分で鏡を見ながら切っていくので割と思い通りにやれているから、行かなくていいかな、と・・・
ハサミでやるとバッサリ切れちゃうから、いつもカッターでやってるんです。
左手で髪を摘まんで、右手で持ったカッターを内側から髪に当て、少しずつ削ぐようにサリサリと。
慣れないと指や耳を切ったりするのでお気を付けください。
髪が乾いていると切りにくいし、切った髪がバラけるので、シャワーを浴びた後だったり、水で濡らしながらやるといいです。
髪を切るって、お店でやると数千円しますよね。
仮に一回3千円として、年に3回行くとして、9千円。それが自分でやればゼロですよ。
生涯で考えると、僕が浮かせる散髪代は数十万くらいになるんじゃないだろうか。
ちなみにこんな感じのゴツイ黒刃カッターで切ってます。切れ味がいいのが大事。

*
以下は大した話じゃないので、僕にそれほど興味のない人は読まないで下さい!
.
.
.
僕の母親は美容師で、実家には美容室が併設されていました。
だから自分で髪を切っている・・・というわけではないから今日の話には全然関係ないんだけど、実家の美容室の光景を思い浮かべる度に、思い出すことがあるんです。
小学校最後の夏休みだったかな。暑い日で、リビングよりもエアコンが効いている美容室の方が涼しくて、お客さんもいなかったから、麦茶を入れたグラスだけ持ってスタイリングチェアに座ってぼんやりしていた。店主である母も台所にいて、店には誰もいなかった。
しばらくして、お客さんが来店したチャイムが流れて、ドアが開いた。
店に入って来たのは、同じ学校に通っている同学年の女の子だった。
その子と特に接点もなかった僕は、挨拶もせずに椅子から立ち、店を出て母を呼びに行った。
その時は、それだけ。同級生が髪を切りに来たんだな、と思うくらいで、何も感じなかった。
(色々と端折って)
その後、中学に上がってから、その女の子が時折見せてくる好意の切れ端みたいなのに少しずつ触れていき、やがて僕はその子を死ぬほど好きになった。
それまでも人を好きになることはあったけれど、その恋は別格だった。感情の大小の尺度で見れば、初恋と言ってもいいし、そう言いたい。
その時期色々あって心が最悪に病んでたし、自分の中の半分はいつでも死にたいとも思っていたけど、その子の存在のおかげで生きていられた。
そして不意に思い出す。以前その子が、うちの美容室に来たことがあったな、と。
もしかしたらそれは、僕に会いに来てたんだろうか、と。
自惚れがないとは言い切れないけど、でもその子の家からうちまでは1km以上あるし、もっと近くに美容室はあるだろうにと思う。
でも、その頃の僕の破滅的な自己嫌悪と人間不信で、結局僕は中学卒業までその子に何も言えなかった。
そうして後から何度も思い出して、「あんなに近くにいたのに」と頭を抱えて何年も後悔に悶えることになるのです。
でも、叶わなかったからこそこの初恋は僕の中できっと永遠に綺麗なままだし、そこで負った傷とか温かな幸福感とか、苦しい後悔とか喪失感みたいなものは、ずっと僕の人生の軸になっているし、それがあるから、小説を書いているんだと思うんです。
もし、絶対ないとは思うけど万が一、その子がこれを読んだら、「あ、これ自分のこと?」って気付くかな。
多分今は、とても幸せに生きているんでしょうね。そうであってほしい。